大空の下に、ねそべる巨人のような大地がありました。
たえず形を変えながら空を流れる雲は、巨人の見る夢だ
といいます。巨人がねむりつづける間に、雨は無数の矢
のようにふりそそぎ、山深い泉は人しれずわき出して一
すじの川となり、ねむる巨人のからだをけずって、とう
とうと流れました。
 さて、谷のこちら側に、ひとりのケ
ンタウルスが住んでいました。ケンタ
ウルスというのは上半身が人間で、腰
から下はつやつやした茶色い毛なみのりっぱな馬のから
だです。それから、いつも、矢をつがえた弓を手にして
いました。これは不思議な弓矢で、ケンタウルス自身に
も、矢がいつ飛ぶか、当たったらどうなるか、わからな
いのでした。
ケンタウルスは野原を駆けながら、ひろびろとした空
を端から端へ動いてゆく雲をながめました。とけ残った
雪の間から、花々の咲きそめる早春でした。
ケンタウルスはがけふちまで来ました。深い谷底を、
白い川が、しぶきを花びらのように散らしながらごうご
うと流れています。ケンタウルスは小手をかざして見お
ろしました。
むこう岸には、一ぴきのカニが住ん
さて、谷のこちら側に、ひとりのケ
ンタウルスが住んでいました。ケンタ
ウルスというのは上半身が人間で、腰
から下はつやつやした茶色い毛なみのりっぱな馬のから
だです。それから、いつも、矢をつがえた弓を手にして
いました。これは不思議な弓矢で、ケンタウルス自身に
も、矢がいつ飛ぶか、当たったらどうなるか、わからな
いのでした。
ケンタウルスは野原を駆けながら、ひろびろとした空
を端から端へ動いてゆく雲をながめました。とけ残った
雪の間から、花々の咲きそめる早春でした。
ケンタウルスはがけふちまで来ました。深い谷底を、
白い川が、しぶきを花びらのように散らしながらごうご
うと流れています。ケンタウルスは小手をかざして見お
ろしました。
むこう岸には、一ぴきのカニが住ん
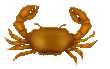 でいました。岩の間につもったやわら
かい泥にからだをなかばうずめて、て
っぺんについた二つの目で、そそりたつ絶壁のかなた、
谷の上の空を流れてゆく雲をながめて暮らしていました。
ケンタウルスはこのカニを見つけました。
「おーい」
かれは手をラッパにして、よく通るいい声で言いました。
「おーい」
カニもケンタウルスに気づいて、さけび返しました。
ふたりはおしゃべりを始めました。ケンタウルスが、
平原をわたって花のにおいを運ぶ春風の話をすると、カ
ニは、岩の間をしたたり落ちる雪どけ水の話をしました。
それから、めいめい、雲の話をすると、ケンタウルスは
言いました。
「谷から見上げても、空の雲は動いていくのだな」
「平原の上の空にも、流れる雲があるんだね」
とカニは答え、うれしいときのくせで、口をパクパクさ
せて、ブクブクあわをふきました。
ケンタウルスもうれしかったので、思わず弓をぎゅっ
とにぎりしめました。すると、弓づるがビュンと鳴って、
矢がひとりでにはなたれました。矢はななめに谷を越え
て飛んでゆき、泥からちらりと出ていたカニの甲らにつ
きささりました。
「大変だ! おーい、だいじょうぶか?」
ケンタウルスはさけびました。
「だいじょうぶ、不思議な矢だね。ちっとも痛くないよ」
カニは元気に答えました。
「それどころか、矢をとおして、あんたの言ってた平原
の春風が感じられる。きっとあんたの心に吹く春風だね」
「そう言えば、わたしの弓づるからは雪どけ水の音が聞
こえる。君の心にひびく歌だな」
ケンタウルスとカニは、しばらくの間、おたがいから
もたらされるものに、心をすませました。けれど、夕暮
れが近くなってくると、ケンタウルスは言いました。
「暗くなる前に、ぜひ、君がするように谷底から雲をな
がめてみたい。そこへゆくから、待っててくれたまえ」
カニは泥の中から小さなはさみをふりました。
「それは無理だ。あんたの馬の足がどんなにりっぱでも、
このがけはけわしすぎる。落ちたら、首の骨を折るよ」
「だいじょうぶだ。それにわたしは、君の教えてくれた
雪どけ水の音もじかに聞きたいのだ」
「ぼくだってあんたの所へ行ってみたいよ。だけど流れ
は急だし、ぼくは横にしか歩けないから、とてもできな
い。あんたもあぶないまねはよすんだ。たとえがけを下
りられても、あんたがおぼれて死んだら、ぼくはもう二
度と春風を感じられなくなってしまう」
けれど、ケンタウルスは、たくましいからだをひるが
えして、がけを下り始めていました。もとより道はなく、
目もくらむ断がいが乱暴におりたたまれたような地形で
す。岩のさけ目のひどいガレ場は、ケンタウルスの黒光
りするひづめがふむたびに、ひっきりなしにガラガラと
くずれました。
にぎりこぶしくらいの石が、ケンタウルスのからだに
ゴツンと当たりました。思わずケンタウルスは四つの足
でよろめきます。はるか下に見える白い川がぐらりとゆ
れました。とたんに、下からそれを見ていたカニまで、
ゴツンといたみをおぼえ、ぐらりとめまいがしました。
カニはさけびました。
「あぶない!」
「何のこれしき、わたしは平気だ」
と、ケンタウルスは笑って答えました。
けれどカニがさけんだとき、手の中で雪どけ水の歌を
歌っていた弓づるがひとりでにビンとふるえて、ケンタ
ウルスのほおをピシリと打ちました。
ケンタウルスは、何度も落ちそうになりました。その
たびにカニは、自分が落ちるかのようなおそろしさを味
わいました。そしてだんだん、矢のささった甲らがいた
くなってきたのです。春風はまだ矢をとおしてカニの心
にふいていましたが、ケンタウルスが岩角で肩をすりむ
いたり、足をすべらせたりするごとに、矢からカニにい
たみが伝わりました。一方、カニがいたみを感じるたび
に、弓はあばれてケンタウルスのからだを打ち、がけ下
りをじゃまするのでした。
ケンタウルスのひたいにつめたい汗がにじんできまし
た。カニはうれしいときのくせのはずだったのに、口を
パクパクさせてあわをふきました。矢のささった甲らの
傷に血がにじみでて、あわがピンク色に染まりました。
あたりは暗くなります。影になった絶壁の中ほどで、
ケンタウルスは苦しそうにあえぎ、とうとう平原の春風
のことを忘れました。影になった谷底の泥の中で、カニ
は矢傷のいたさにうめき、とうとう雪どけ水の歌を忘れ
ました。
そのとき、カニがさけびました。
「ケンタウルス、このままじゃあんたは、谷に落ちてし
まう。ぼくの目の前で首を折るのは、それだけは、やめ
てくれ」
「今さら引き返せるものか」
と、ケンタウルスは、いうことをきかない弓を必死に押
さえようとしながら、息もたえだえにさけび返しました。
「もうがけの上に戻ることもできない」
「その弓を捨てるんだ」
と、カニは赤いあわをブクブクはきながら言いました。
「これじゃ、ふたりともおしまいだ。弓を捨てて、ひき
返してくれ。どうか、たのむよ」
「この弓とその矢は、わたしと君とをつなぐたった一つ
のきずなだ。どうして捨てられよう?」
そう言ったケンタウルスのほおを、なみだが一すじつ
たいました。それはケンタウルスのりっぱな灰色のあご
ひげの先から、はるか下のはげしい流れに落ちました。
「その弓矢こそが、ぼくとあんたを傷つけるんだ」
そう答えたカニの甲らにも、なみだが一すじつたいま
した。それは泥にしみ、川に流れこんでいきました。
「では君は、わたしの弓矢をにくむのか」
すっかり暗くなって、カニは目がきかなくなり、ただケ
ンタウルスの声だけが聞こえてきました。
「そんなことはない。ケンタウルスの魔法の矢で春風を
感じるなんて、だれにでもできるもんじゃない。ただぼ
くが矢に当たったために、あんたまで傷つくのがつらい」
ケンタウルスも、がけにしがみつくのがやっとで、カニ
の姿を見ることはできませんでした。けれども、カニの
言葉が聞こえたとき、弓はふっと静まって、ケンタウル
スを打つのをやめました。矢をとおしてカニにもそれが
わかりました。
「今だ。弓を捨てろ! ぼくも矢をしまつする。さあ!」
そう言うとカニは両のはさみで力いっぱい甲らから矢
をぬきとり、白い川の方へ、思いきりとおく投げました。
そしてそのとき、ケンタウルスの手から投げられた弓が、
銀に光りながら流れ星のように谷底へ落ちてくるのを見
ました。
弓と矢は、暗やみに白いしぶきをあげて川に落ちまし
た。はげしい流れがあっという間に二つをさらってゆき
ました。
もといた平原に帰るには、ケンタウルスは、やみの中
でがけ登りをしなければなりませんでした。けれど弓が
なくなったので、四つの足と両手を使って、星明かりを
たよりに登りました。真夜中すぎ、かれはようやくがけ
の上に立ちました。
「おーい」
手をラッパにして呼びながら見下ろすと、今しものぼ
ってきたあわい、白い、花びらのようなレモン形の月が
谷底をてらしました。荒れ下る川のほとりの黒い泥の中
に、カニの小さな甲らが銀貨のように光っているのが見
えました。
「月だよ。月が見える」
と、カニの声がとどいてきました。
「そこからも見えるか」
「ああ、よく見える。そこからも見えるんだね」
「見えるとも」
ケンタウルスは少し口をつぐんだあとで、
「わたしはこの川のゆきつく先まで行ってみよう。どこ
へ流れてゆくのか、知りたくなった」
「ぼくは知っている。行ったことはないけれど」
と、カニの声が聞こえました。
「とおいむかし、カニはそこから来たんだ。だからいつ
も夢に見るよ」
弓矢があればその夢をわたしも見ることができたのに、
と、ケンタウルスは思いましたが、それは言わずにおき
ました。
ケンタウルスはいく日も谷にそって平原を旅しました。
春がすぎ、夏がゆき、秋が訪れ、冬が去ってゆきました。
そうしていつの日か、ケンタウルスはゆきつくのです
──海へ。そしてあんなにはげしく荒れくるっていた川
も、ゆったりとおだやかな流れとなってかえってゆく、
その大きな河口の浜辺で、ケンタウルスはいつの日か、
砂になかばうもれたかれの銀の弓矢を拾いあげるのです。
おわり
(雑誌「児童文芸」92年5月号に掲載)
でいました。岩の間につもったやわら
かい泥にからだをなかばうずめて、て
っぺんについた二つの目で、そそりたつ絶壁のかなた、
谷の上の空を流れてゆく雲をながめて暮らしていました。
ケンタウルスはこのカニを見つけました。
「おーい」
かれは手をラッパにして、よく通るいい声で言いました。
「おーい」
カニもケンタウルスに気づいて、さけび返しました。
ふたりはおしゃべりを始めました。ケンタウルスが、
平原をわたって花のにおいを運ぶ春風の話をすると、カ
ニは、岩の間をしたたり落ちる雪どけ水の話をしました。
それから、めいめい、雲の話をすると、ケンタウルスは
言いました。
「谷から見上げても、空の雲は動いていくのだな」
「平原の上の空にも、流れる雲があるんだね」
とカニは答え、うれしいときのくせで、口をパクパクさ
せて、ブクブクあわをふきました。
ケンタウルスもうれしかったので、思わず弓をぎゅっ
とにぎりしめました。すると、弓づるがビュンと鳴って、
矢がひとりでにはなたれました。矢はななめに谷を越え
て飛んでゆき、泥からちらりと出ていたカニの甲らにつ
きささりました。
「大変だ! おーい、だいじょうぶか?」
ケンタウルスはさけびました。
「だいじょうぶ、不思議な矢だね。ちっとも痛くないよ」
カニは元気に答えました。
「それどころか、矢をとおして、あんたの言ってた平原
の春風が感じられる。きっとあんたの心に吹く春風だね」
「そう言えば、わたしの弓づるからは雪どけ水の音が聞
こえる。君の心にひびく歌だな」
ケンタウルスとカニは、しばらくの間、おたがいから
もたらされるものに、心をすませました。けれど、夕暮
れが近くなってくると、ケンタウルスは言いました。
「暗くなる前に、ぜひ、君がするように谷底から雲をな
がめてみたい。そこへゆくから、待っててくれたまえ」
カニは泥の中から小さなはさみをふりました。
「それは無理だ。あんたの馬の足がどんなにりっぱでも、
このがけはけわしすぎる。落ちたら、首の骨を折るよ」
「だいじょうぶだ。それにわたしは、君の教えてくれた
雪どけ水の音もじかに聞きたいのだ」
「ぼくだってあんたの所へ行ってみたいよ。だけど流れ
は急だし、ぼくは横にしか歩けないから、とてもできな
い。あんたもあぶないまねはよすんだ。たとえがけを下
りられても、あんたがおぼれて死んだら、ぼくはもう二
度と春風を感じられなくなってしまう」
けれど、ケンタウルスは、たくましいからだをひるが
えして、がけを下り始めていました。もとより道はなく、
目もくらむ断がいが乱暴におりたたまれたような地形で
す。岩のさけ目のひどいガレ場は、ケンタウルスの黒光
りするひづめがふむたびに、ひっきりなしにガラガラと
くずれました。
にぎりこぶしくらいの石が、ケンタウルスのからだに
ゴツンと当たりました。思わずケンタウルスは四つの足
でよろめきます。はるか下に見える白い川がぐらりとゆ
れました。とたんに、下からそれを見ていたカニまで、
ゴツンといたみをおぼえ、ぐらりとめまいがしました。
カニはさけびました。
「あぶない!」
「何のこれしき、わたしは平気だ」
と、ケンタウルスは笑って答えました。
けれどカニがさけんだとき、手の中で雪どけ水の歌を
歌っていた弓づるがひとりでにビンとふるえて、ケンタ
ウルスのほおをピシリと打ちました。
ケンタウルスは、何度も落ちそうになりました。その
たびにカニは、自分が落ちるかのようなおそろしさを味
わいました。そしてだんだん、矢のささった甲らがいた
くなってきたのです。春風はまだ矢をとおしてカニの心
にふいていましたが、ケンタウルスが岩角で肩をすりむ
いたり、足をすべらせたりするごとに、矢からカニにい
たみが伝わりました。一方、カニがいたみを感じるたび
に、弓はあばれてケンタウルスのからだを打ち、がけ下
りをじゃまするのでした。
ケンタウルスのひたいにつめたい汗がにじんできまし
た。カニはうれしいときのくせのはずだったのに、口を
パクパクさせてあわをふきました。矢のささった甲らの
傷に血がにじみでて、あわがピンク色に染まりました。
あたりは暗くなります。影になった絶壁の中ほどで、
ケンタウルスは苦しそうにあえぎ、とうとう平原の春風
のことを忘れました。影になった谷底の泥の中で、カニ
は矢傷のいたさにうめき、とうとう雪どけ水の歌を忘れ
ました。
そのとき、カニがさけびました。
「ケンタウルス、このままじゃあんたは、谷に落ちてし
まう。ぼくの目の前で首を折るのは、それだけは、やめ
てくれ」
「今さら引き返せるものか」
と、ケンタウルスは、いうことをきかない弓を必死に押
さえようとしながら、息もたえだえにさけび返しました。
「もうがけの上に戻ることもできない」
「その弓を捨てるんだ」
と、カニは赤いあわをブクブクはきながら言いました。
「これじゃ、ふたりともおしまいだ。弓を捨てて、ひき
返してくれ。どうか、たのむよ」
「この弓とその矢は、わたしと君とをつなぐたった一つ
のきずなだ。どうして捨てられよう?」
そう言ったケンタウルスのほおを、なみだが一すじつ
たいました。それはケンタウルスのりっぱな灰色のあご
ひげの先から、はるか下のはげしい流れに落ちました。
「その弓矢こそが、ぼくとあんたを傷つけるんだ」
そう答えたカニの甲らにも、なみだが一すじつたいま
した。それは泥にしみ、川に流れこんでいきました。
「では君は、わたしの弓矢をにくむのか」
すっかり暗くなって、カニは目がきかなくなり、ただケ
ンタウルスの声だけが聞こえてきました。
「そんなことはない。ケンタウルスの魔法の矢で春風を
感じるなんて、だれにでもできるもんじゃない。ただぼ
くが矢に当たったために、あんたまで傷つくのがつらい」
ケンタウルスも、がけにしがみつくのがやっとで、カニ
の姿を見ることはできませんでした。けれども、カニの
言葉が聞こえたとき、弓はふっと静まって、ケンタウル
スを打つのをやめました。矢をとおしてカニにもそれが
わかりました。
「今だ。弓を捨てろ! ぼくも矢をしまつする。さあ!」
そう言うとカニは両のはさみで力いっぱい甲らから矢
をぬきとり、白い川の方へ、思いきりとおく投げました。
そしてそのとき、ケンタウルスの手から投げられた弓が、
銀に光りながら流れ星のように谷底へ落ちてくるのを見
ました。
弓と矢は、暗やみに白いしぶきをあげて川に落ちまし
た。はげしい流れがあっという間に二つをさらってゆき
ました。
もといた平原に帰るには、ケンタウルスは、やみの中
でがけ登りをしなければなりませんでした。けれど弓が
なくなったので、四つの足と両手を使って、星明かりを
たよりに登りました。真夜中すぎ、かれはようやくがけ
の上に立ちました。
「おーい」
手をラッパにして呼びながら見下ろすと、今しものぼ
ってきたあわい、白い、花びらのようなレモン形の月が
谷底をてらしました。荒れ下る川のほとりの黒い泥の中
に、カニの小さな甲らが銀貨のように光っているのが見
えました。
「月だよ。月が見える」
と、カニの声がとどいてきました。
「そこからも見えるか」
「ああ、よく見える。そこからも見えるんだね」
「見えるとも」
ケンタウルスは少し口をつぐんだあとで、
「わたしはこの川のゆきつく先まで行ってみよう。どこ
へ流れてゆくのか、知りたくなった」
「ぼくは知っている。行ったことはないけれど」
と、カニの声が聞こえました。
「とおいむかし、カニはそこから来たんだ。だからいつ
も夢に見るよ」
弓矢があればその夢をわたしも見ることができたのに、
と、ケンタウルスは思いましたが、それは言わずにおき
ました。
ケンタウルスはいく日も谷にそって平原を旅しました。
春がすぎ、夏がゆき、秋が訪れ、冬が去ってゆきました。
そうしていつの日か、ケンタウルスはゆきつくのです
──海へ。そしてあんなにはげしく荒れくるっていた川
も、ゆったりとおだやかな流れとなってかえってゆく、
その大きな河口の浜辺で、ケンタウルスはいつの日か、
砂になかばうもれたかれの銀の弓矢を拾いあげるのです。
おわり
(雑誌「児童文芸」92年5月号に掲載)
|